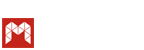
 电话:400-888-1119
电话:400-888-1119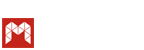
 电话:400-888-1119
电话:400-888-1119佛山市欧曼美格家具有限公司成立于2003年,凭借品牌“美格利生”享誉全球。欧曼美格是一家集研发、设计、制造及销售于一体的大型家具生产企业,总部位于佛山市南海区九江镇,拥有15000平方米的智能制造基地。公司拥有丰富的产品体系和个性化定制优势, 涵盖办公家、宿舍家具、医养家具等行业板块,凭借强大的设计研发能力,荣获佛山市细分行业龙头企业,和国家级高新技术企业等荣誉称号。


随着现代企业对办公环境的要求越来越高,办公家具不仅仅是简单的桌椅板凳,更是展示企业文化和员工工作状态的重要载体。作为专业的办公家具定制厂家-美格利生,我们深知每一个细节的重要性...
在个性化需求越来越强烈的市场趋势下,定制办公家具可以满足不同场景和行业人士的使用需求,也变得越来越受欢迎了。但是很多消费者却因为定制的时间一直干到困扰,那到底多久的货期才是合...
现在很多学生从初中就开始住校了,那么住校就需要聊到宿舍床了,为了购买到合适尺寸的床上用品,所以很多人问到学生宿舍床的尺寸一般是多少?下面欧曼作为一家公寓床厂家给大家聊聊宿舍床...